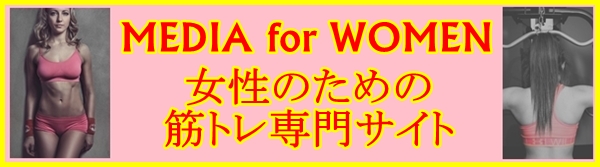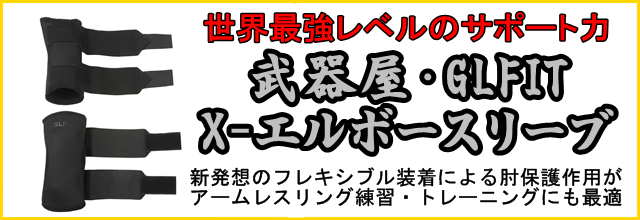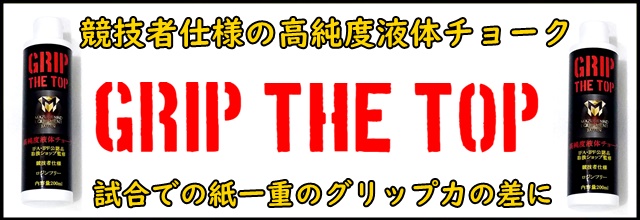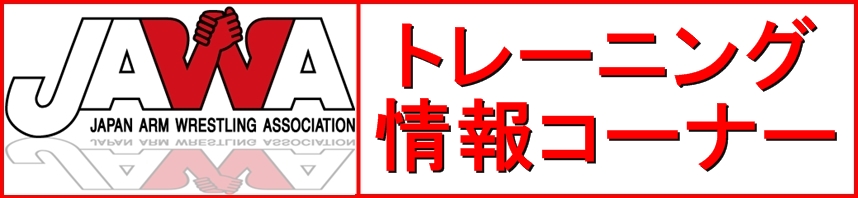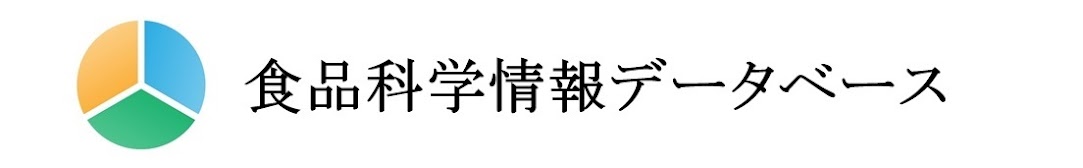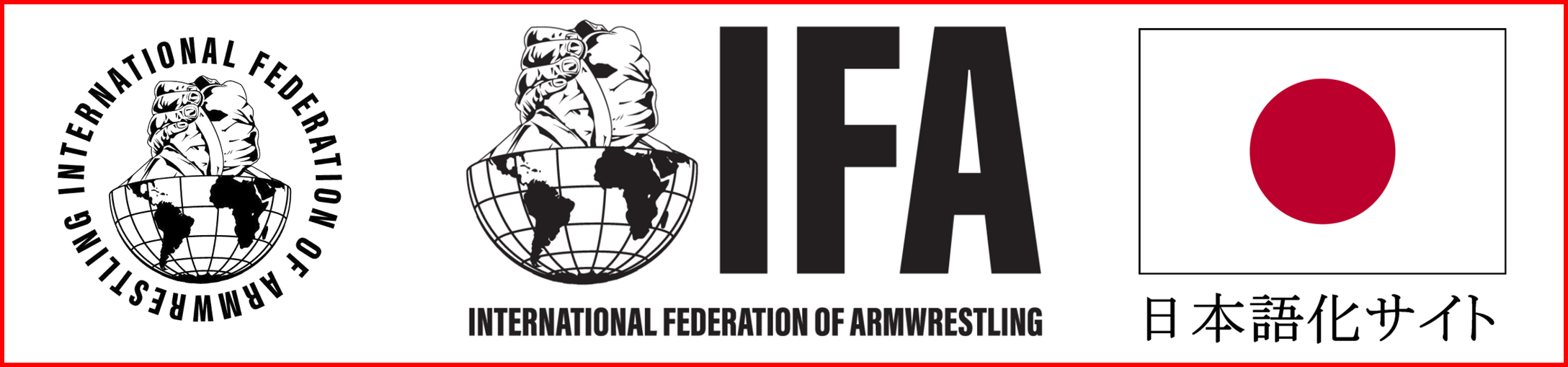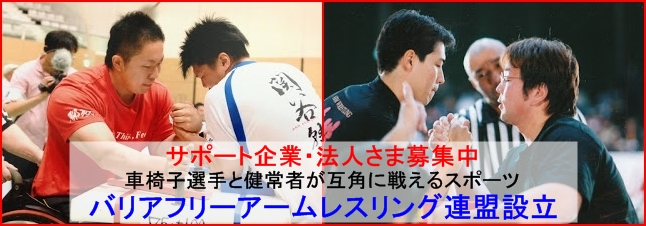バーベルトレーニングでの鍛え方を、胸筋・背筋・腕・肩・腹筋・下半身それぞれのメニューから厳選して詳しく解説するとともに、具体的な一週間の筋トレプログラムを例示します。
※本記事の記載内容は、当ジムでの指導実績に基づいています。
※本記事は提供元サイト(BUKIYA-MOBILE/武器屋.net)より転載・出力しています。著作権・コンテンツ権・引用および免責事項についてはこちらをご参照ください。

※本記事は世界チャンピオン金井選手・山田選手も所属し、ワールドゲームズや国体にも参加実績のある公式競技団体「JAWA」の情報記事として公開されています。
※当サイトでは、科学的に正しい記載を行うことを第一に考えており、「厚生労働省|eヘルスネット」および公共性の高い情報サイトである「Wikipedia」からエビデンスを担保しています。主なエビデンスに関してはこちらのページでご確認ください。
■バーベル筋トレの特徴
●トレーニングの基本かつ最強レベル

バーベルトレーニングは、全てのウエイトトレーニングの基本となる方法で、なおかつ、最強レベルの筋トレ方法です。
その理由は、まず第一に両手でウエイトを保持するので、ダンベルなど他のフリーウエイトトレーニングに比べ、圧倒的な高負荷を筋肉にかけることができるからです。
そして、マシントレーニングに比べ、ウエイトのブレを自身の体幹インナーマッスルで支える必要があるため、芯から身体が強くなるからです。
●筋トレbig3とは?
一般的に筋トレbig3と呼ばれるウエイトトレーニングは、バーベルベンチプレス・バーベルデッドリフト・バーベルスクワットの三種目で、このビック3だけを行っても十分な筋トレ効果があります。
各種目が効果のある主な筋肉部位は以下の通りです。
◯バーベルベンチプレス
大胸筋・三角筋・上腕三頭筋
◯バーベルデッドリフト
広背筋・僧帽筋・上腕二頭筋
◯バーベルスクワット
大腿四頭筋・ハムストリングス
■筋トレ目的に合わせた重量設定

バーベルトレーニングを始めるにあたって、まず知っておきたいのが筋トレの目的別の重量設定の方法で、そのためには筋肉を構成する3種類の筋繊維の特徴を理解しなくてはいけません。それは、以下の通りです。
●ターゲットにする筋繊維に最適な反復回数

筋肉を構成している筋繊維には主に三種類があり、それは、筋繊維TYPE2b(速筋|FG筋)、筋繊維TYPE2a(速筋|FO筋)、筋繊維TYPE1(遅筋|SO筋)で、それぞれの特徴と鍛えるのに適切な反復回数は以下の通りです。
●筋繊維TYPE2b(速筋|FG筋)
収縮が速く(Fast)、グリコーゲン(Glycogen)を消費する速筋で、FG筋とも呼ばれます。30秒以内の瞬発的な動作で爆発的に収縮し、鍛えると強く筋肥大します。筋肥大バルクアップ筋トレのターゲットとなる筋繊維で、10回前後の反復回数で限界がくるような高負荷設定でトレーニングします。
●筋繊維TYPE2a(速筋|FO筋)
収縮が比較的速く(Fast)、酸素(Oxygen)と脂肪酸を消費する速筋で、FO筋とも呼ばれます。60秒以内の持久要素のある瞬発的な動作で収縮し、鍛えるとある程度の筋肥大が起こります。細マッチョ筋トレや女性の部分ボリュームアップのターゲットとなる筋繊維で、15回前後の反復回数で限界がくる中負荷設定でトレーニングします。
●筋繊維TYPE1(遅筋|SO筋)
収縮が比較的遅く(Slow)、酸素(Oxygen)と脂肪酸を消費する遅筋で、SO筋とも呼ばれます。60秒以上の持久的な動作で持続的に収縮し、鍛えると筋密度が向上し引き締まります。引き締めダイエット筋トレのターゲットとなる筋繊維で、20回以上の反復回数で限界がくる低負荷設定でトレーニングします。
■全身の主な筋肉を知る
●トレーニングの基本として重要

筋肉を鍛えていく上で、重要なのが全身の主な筋肉のグループ分けとそれぞれの作用を知ることです。
全身の筋肉は、主に4つのグループに分けられ、それぞれの主な作用は以下の通りです。
●上半身の押す筋肉グループ
◯大胸筋
胸の筋肉で腕を前に押し出す・前で閉じる作用がある
◯三角筋
肩の筋肉で腕を上・横・前・後ろに上げる作用がある
◯上腕三頭筋
腕の後ろの筋肉で肘を伸ばす作用がある
●上半身の引く筋肉グループ
◯広背筋
背中の筋肉で腕を上や前から引き寄せる作用がある
◯僧帽筋
背中の筋肉で腕を下から引き寄せる作用がある
◯上腕二頭筋
腕の前の筋肉で肘を曲げる作用がある
●体幹の筋肉グループ
◯腹筋群
体幹前側の筋肉で胴体を曲げる・捻る作用がある
◯脊柱起立筋群
体幹後ろ側の筋肉で胴体を伸ばす作用がある
●下半身の筋肉グループ
◯大腿四頭筋
太腿前側の筋肉で膝を伸ばす作用がある
◯ハムストリングス
太腿後ろ側の筋肉で膝を伸ばす作用がある
◯臀筋群
お尻の筋肉で股関節を伸ばす作用がある
以上は、あくまでも筋トレをしていく上で、最低限知っておくべき筋肉で、このほかの数多くの筋肉があります。
▼さらに詳しい筋肉の構造と作用
【筋肉部位名称スマホ完全図鑑】胸・背中・腕・腹・下半身・インナーマッスルの名前と鍛え方
■バーベル筋トレの適切な頻度は?
●超回復を考慮して部位分割で週3回がベスト

バーベル筋トレにかぎらず、全てのウエイトトレーニングは超回復理論にのっとり、適切な頻度で実施していく必要があります。
●超回復とは?
筋肉を構成する筋繊維は、トレーニングでよって負荷を受けると微細な裂傷が生じ、24~72時間の回復期間を経て「元よりも強く太く回復」します。これを、超回復と言い、人間の筋肉に備わった生体反応で、これを利用して身体を作っていくのが筋トレの基本理論です。
ですので、バーベルトレーニングで身体を作っていく場合も、当然、超回復理論にのっとる必要があります。
実際、全身を一度に鍛えると、次のトレーニングまでには最低でも72時間の休息が必要となり、週2回のトレーニングが限界となります。これでは、非効率ですので、全身の筋肉を3つのグループに分け、ローテーションで週3回のトレーニングを行うのが効率的です。
このような方法を部位分割法=スプリットトレーニングと言い、以下のように部位分割するのが一般的です。
①上半身の押す筋肉グループ(大胸筋・三角筋・上腕三頭筋+腹筋群)
②上半身の引く筋肉グループ(広背筋・僧帽筋・上腕二頭筋+腹筋群)
③下半身の筋肉グループ(大腿四頭筋・ハムストリングス・臀筋群)
それでは、次の項目では筋肉部位別のバーベルトレーングメニューを解説していきます。
■大胸筋のバーベルトレーニング
●バーベルベンチプレス

バーベルベンチプレスは大胸筋を中心として、三角筋や上腕三頭筋にも効果的な、上半身の押す作用の筋肉の基本となるバーベルトレーニングです。
バーベルベンチプレスは、まず、ベンチに仰向けになり、肩甲骨を寄せ、80cm前後の手幅でシャフトをグリップします。
先にグリップをしてしまうと、肩甲骨の寄せが足らなくなる場合もありますので、必ず「肩甲骨を寄せきる」→「シャフトをグリップする」の順で行ってください。
次に肩甲骨をベンチに強く押しつけ、足で上半身を押し込むようにしてブリッジを作ります。
そして、腰をベンチに下ろし肩甲骨二点と合わせて三点で上半身を保持します。

こちらの画像(youtubeより)は女性のものですが、上級者の作る理想的なベンチプレスのブリッジですので、ご参照ください。
ブリッジを作ったらバーベルをラックアウトしますが、いきなり胸に下ろすのではなく、まず胸の真上まで水平移動してから下ろします。
バーベルを下ろす前に、大きく息を胸にためますが、この胸郭の膨らみも重要な要素ですので、バーベルを下ろし、上げ終わるまでは息をためたままにしてください。
胸郭の膨らみを作ったら、バーベルを下ろしていきますが、この時に勢いをつけて胸の上でバウンドさせないことも大切です。
バウンドを補助に使うと、高重量を挙げやすくなりますが、あくまでそれはチーティングであり、胸の筋肉に対しては効果が低くなります。
胸の上でバーベルが一瞬静止するくらいのつもりで、丁寧に筋力でコントロールしてバーベルを下ろしていきましょう。
バーベルを胸の上に下ろしたら、肩甲骨を寄せたままバーベルを押し上げていきます。この時に、肩甲骨の寄せ方が甘いと、肩から初動することになり肩関節を痛めるリスクがありますので、セット中は常に肩甲骨を寄せ、ブリッジが崩れないように注意してください。
バーベルを押し上げたら、その位置で軽く顎を引いて大胸筋を完全収縮させます。
よくある間違った動作として、つい頭をベンチに押しつけるケースがありますが、大胸筋の収縮に対する首の連動方向は顎を引く方向です。
頭を後ろに押しつけると、首を痛めるリスクがあるだけでなく、大胸筋の完全収縮を妨げますので注意してください。
【正しいやり方と手順】
①ベンチに仰向けになり、肩甲骨を強く寄せ、シャフトをグリップする
②肩甲骨をベンチに押しつけ、足で上半身を押し込むようにブリッジを作り、腰をおろす
③バーベルをラックアウトし、胸の真上まで水平移動してから、コントロールして胸の上に下ろす
④肩甲骨を寄せたままバーベルを押し上げ、顎を引いて大胸筋を完全収縮させる
なお、下記の記事は、パワーリフティング元全日本王者(種目別ベンチプレス世界二位)の方が、初心者がベンチプレスで100kgの壁を突破するまでにやるべきことを詳細に執筆した記事です。
是非、ご参照ください。

▼全日本王者執筆記事
【ベンチプレス100kgを挙げるやり方】フォームとメニューの組み方を元全日本王者が解説
●インクラインベンチプレス

インクラインバーベルベンチプレスは大胸筋上部に集中的な効果があるバーベルトレーニングです。
インクラインバーベルベンチプレスは、インクラインベンチに仰向けになり、肩甲骨を寄せ、シャフトを80cm程度の手幅でグリップして構えます。
構えたら、バーベルをラックアウトし、胸の真上まで水平移動してから胸に下ろしていきます。この時に、シャフトをバウンドさせないよう、筋力でコントロールして下ろしてください。
バーベルを胸まで下ろしたら、肩甲骨を寄せたままバーベルを押し上げます。
セット終盤で苦しい時などは、つい腰を浮かせがちですが、腰を浮かせてしまうと大胸筋上部に有効な軌道が失われますので、最後までシートに腰をつけて押し上げるのが大切なポイントです。
また、大胸筋と首の連動性を考慮し、バーベルを押し上げた位置でやや顎を引くことで、大胸筋上部が完全収縮して効果が高まります。
【正しいやり方と手順】
①インクラインベンチに仰向けになり、肩甲骨を寄せてシャフトをグリップする
②バーベルを胸の真上まで水平移動させ、コントロールしながら胸に下ろす
③肩甲骨を寄せたままバーベルを押し上げ、顎を引いて大胸筋上部を完全収縮させる
●デクラインベンチプレス

デクラインバーベルベンチプレスは大胸筋下部に集中的な効果があります。
デクラインバーベルベンチプレスは、デクラインベンチに仰向けになり、肩甲骨を寄せ、80cm程度の手幅でグリップして構えます。
そこから、バーベルをラックアウトし、胸の真上まで水平移動してからバーベルを胸の上に下ろしていきますが、この時にバーベルがバウンドしないように、しっかりと筋力でコントロールさせることが大切です。
バーベルを胸まで下ろしたら、肩甲骨を寄せたままバーベルを押し上げていきます。肩甲骨の寄せ方が甘いと、肩から初動することになり、肩関節に強い負担がかかりますので、完全に肩甲骨を寄せるイメージを持って動作を行ってください。
また、大胸筋と首の連動性から、バーベルを押し上げた位置でやや顎を引くことで大胸筋下部が完全収縮して効果が高まります。
【正しいやり方と手順】
①デクラインベンチに仰向けになり、肩甲骨を寄せて構える
②バーベルをラックアウトし、胸の真上まで水平移動してから胸に下ろす
③肩甲骨を寄せたままバーベルを押し上げ、顎を引いて大胸筋下部を完全収縮させる
●ワイドグリップベンチプレス

バーベルワイドグリップベンチプレスは大胸筋外側に効果的なバーベルトレーニングです。
バーベルワイドグリップベンチプレスは、ベンチに仰向けになり、通常のグリップよりも拳一つ分ほど手幅を広くグリップし、肩甲骨を確実に寄せて構えます。
ベンチプレス系種目では、肩甲骨の寄せ方が甘いと、肩から初動することになり肩関節に強い負担がかかりますが、なかでもワイドグリップベンチプレスは、非常に強い負担が肩関節にかかりやすいので、特に注意してください。
構えたら、バーベルをラックアウトし、胸の真上まで水平移動してから胸に下ろします。
胸にバーベルを下ろしたら、肩甲骨を寄せたままバーベルを押し上げますが、本種目では、完全に肘が伸びきるまで押し込む必要はあまりありません。
これは、大胸筋外側に負荷がかかるのが、腕を開いて下ろした位置だからです。
ですので、押し上げてからではなく、押し上げる初動を大切にトレーニングを行ってください。
【正しいやり方と手順】
①ベンチに仰向けになり、肩甲骨を寄せ、広い手幅でグリップして構える
②バーベルをラックアウトし、胸の真上まで水平移動してから胸に下ろす
③肩甲骨を寄せたままバーベルを押し上げ、肘が伸びきる直前で再びバーベルを下ろす
●リバースグリップベンチプレス

バーベルリバースグリップベンチプレスはインクラインベンチなしでも大胸筋上部を鍛えられるバーベルトレーニングです。
バーベルリバースグリップベンチプレスは、通常のバーベルベンチプレスとは逆の逆手でシャフトをグリップして行いますが、絶対に守っていただきたいこととして「はじめからリバースグリップでラックアウトしない」ことが挙げられます。
リバースグリップでのバーベルの保持は、ただでさえバーベルが頭側に流れやすいのですが、はじめから頭側にあるラックからバーベルを外すと、頭側にバーベルが落下するのを止められません。
必ずノーマルグリップでラックアウトし、胸の上にバーベルを下ろしてからグリップを逆手に握り直してください。
どうしても、はじめからリバースグリップでラックアウトしたい場合は、左右に二人の補助者をつけるようにします。
なお、本種目はバーベルのブレを抑えるのが難しく、初心者の方にはおすすめしませんが、チャレンジしたい場合は、補助者をつけ、かなり軽めの重量設定で安全に行ってください。
【正しいやり方と手順】
①ベンチに仰向けになり、ノーマルグリップでシャフトをグリップして構える
②バーベルをラックアウトしたら、胸の上に下ろす
③グリップを逆手にしてバーベルを押し上げる
④セットはバーベルを胸の上に置いた位置で終わり、グリップをノーマルに握りかえてバーベルをラックする
●ベントアームバーベルプルオーバー

ベントアームバーベルプルオーバーは、肘を曲げたまま行うバリエーションで、大胸筋に対して縦方向の負荷が加わります。
仰向けになり、バーベルを胸の上で構え、そこから肘を曲げて頭の後ろに下ろしていきます。
バーベルを最大限下ろしたら、息をためたまま、肘も曲げたままでバーベルを引き上げていき、最後に肩甲骨を解放して体幹前側を縮めるように大胸筋を収縮させてください。
【正しいやり方と手順】
①仰向けになり、バーベルを胸の上で構える
②肘を曲げてバーベルを頭の後ろに下ろす
③肘を曲げたままバーベルを引き上げていき、最後に肩甲骨を解放して大胸筋を完全収縮させる
■三角筋のバーベルトレーニング
●バーベルショルダープレス

バーベルショルダープレスは三角筋全体に効果的なバーベルトレーニングです。
バーベルショルダープレスには、立って行うスタンディングバーベルショルダープレスと座って行うシーテッドバーベルショルダープレスとがあり、それぞれの特徴は次の通りです。
◯スタンディングバーベルショルダープレス
立って行うバリエーションで、膝の屈伸を使ってセルフ補助ができるので、高負荷で追い込むのに適していますが、初心者の方はチーティングを使いすぎる傾向にあるので、中級者以上におすすめです。
◯シーテッドバーベルショルダープレス
膝の屈伸や反動が使えないので、じっくりと確実に追い込むのに適しています。初心者の方におすすめの、基本となるバリエーションです。
このような特徴がありますが、本記事では基本となるシーテッドバーベルショルダープレスについて解説していきます。
まず、シートに座り、胸を張り背すじを伸ばし、肩幅より広くシャフトをグリップして構え、そこからバーベルをラックアウトして肩のラインで構えます。
構えたら、バーベルを真上に押し上げていきますが、この時に背中を反らせすぎて肘が体幹の後ろ側に入らないようにすることが大切です。
肘が体幹の後ろを通る軌道になると、肩関節に強い開き負荷がかかり故障の原因となりますので、必ず肘は体幹の前側を通過するようにしてください。
バーベルを真上に押し上げたら、同じ軌道でゆっくりと効かせながら元に戻ります。本種目は、バーベルを押し上げる時のコンセントリック収縮(短縮性収縮)で三角筋の前部と中部に、ウエイトに耐えながらバーベルを下ろす時のエキセントリック収縮(伸長性収縮)で三角後部に効果があります。
バーベルを下ろす時も、しっかりとコントロールして効かせてください。
【正しいやり方と手順】
①ベンチに座り、胸を張り背すじを伸ばし、肩幅より広くバーベルシャフトをグリップする
②バーベルをラックアウトすし肩のラインで構える
③背中を反らせすぎず、肘が身体の前側を通過する軌道でバーベルを押し上げる
④ゆっくりと効かせながら元に戻る
●バーベルアップライトロー

バーベルアップライトローイングは三角筋に効果的で比較的動作が簡単なバーベルトレーニングです。
バーベルアップライトローイングは、肩幅程度に足を開き、胸を張り背すじを伸ばし、肩幅程度の手幅でシャフトをグリップして構えます。
そこから、肘を先行させてバーベルを顎へ向かって引き上げていきますが、この時に肩甲骨を寄せないことが大切です。
三角筋は背筋群と隣接しているため、肩甲骨を寄せると負荷の大部分が僧帽筋に分散してしまいます。ですので、セット中は常に肩甲骨を解放しておくイメージで動作を行ってください。
バーベルを引き上げたら、そこからゆっくりとウエイトに耐えながらバーベルを下ろしていきます。
本種目は、バーベルを引き上げる時に三角筋の前部と中部に、ウエイトに耐えながら下ろす時に三角筋後部に負荷がかかりますので、戻りの動作も重要です。
また、肘を前に張り出すと三角筋前部に、横に張り出すと三角に中部に、後ろに引き気味にすると三角筋後部に負荷がかかります。
【正しいやり方と手順】
①胸を張り背すじを伸ばし、肩幅程度の手幅でシャフトをグリップして構える
②肘を先行させ、肩甲骨は寄せずにバーベルを引き上げる
③ゆっくりと効かせながら元に戻る
●バーベルフロントレイズ

バーベルフロントレイズは三角筋前部に集中的な効果があるバーベルトレーニングです。
バーベルフロントレイズは、胸を張り背すじを伸ばし、腕を下ろし、肩幅程度の手幅でシャフトをグリップして構えます。
そこから肘を伸ばしたまま腕を前に上げていきますが、この時に上半身を反らせたり、肩甲骨を寄せてしまわないようにすることが大切です。
三角筋は背筋群に隣接しており、上半身を後傾させたり肩甲骨を寄せると、負荷の多くが背筋群(特に僧帽筋)に分散してしまいますので注意が必要になります。
腕を床と平行になる高さまで上げたら、そこから筋力でコントロールしてバーベルを下ろします。
【正しいやり方と手順】
①胸を張り背すじを伸ばし、肩幅程度の広さでバーベルをグリップして構える
②上半身を後傾させたり、肩甲骨を寄せずに、肘を伸ばしたまま腕を前に上げる
③腕を床と並行になるまで上げたら、筋力でコントロールしながら元に戻る
●バーベルリアデルタロー

バーベルリアデルタローは三角筋後部に集中的な効果があるバーベルトレーニングです。
バーベルリアデルタローは、肩幅よりやや広い手幅でバーベルをグリップし、ニーベントスタイルで構えます。
ニーベントスタイルはウエイトトレーニングの基本となる姿勢の一つで、胸を張り背すじを伸ばし、膝がつま先より前に出ないようお尻を引いて前傾姿勢になるフォームです。
ニーベントスタイルで構えたら、そこから肩甲骨を寄せずにバーベルを胸に向けて引き上げていきますが、背筋群に隣接・連動している三角筋後部の特性上、肩甲骨を寄せてしまうと僧帽筋に負荷が逃げてしまいますので、肩甲骨を寄せないイメージで動作を行ってください。
バーベルを引き上げたら、そこから元に戻していきます。この時に、勢いで戻るのではなく、筋力である程度コントロールして効かせながら戻ることも大切です。
【正しいやり方と手順】
①肩幅よりやや広くバーベルをグリップし、ニーベントスタイルで構える
②肩甲骨を寄せずにバーベルを胸に引き上げる
③筋力でコントロールしながら元に戻る
■上腕三頭筋のバーベルトレーニング
●ナローグリップベンチプレス

バーベルナローグリップベンチプレスは上腕三頭筋に効果的なバーベルトレーニングです。
バーベルナローグリップベンチプレスは、ベンチに仰向けになり、肩甲骨を寄せ、肩幅程度の狭い手幅でシャフトをグリップして構えます。
肩幅より狭く手幅を設定すると、バーベルを下ろした時に手首関節に強い捻れ負荷がかかりますので、あまり手幅は狭くしすぎないようにして下さい。
構えたら、バーベルをラックアウトし、胸の真上まで水平移動してから胸に下ろしていきます。この時に、あまり肘を外に張り出すと、これも手首関節に強い負担がかかりますから、あまり肘を張り出さず体側に沿わせるように動作を行うのがポイントです。
バーベルを胸の上に下ろしたら、肩甲骨を寄せたまま、下ろした時と同じ軌道でバーベルを押し上げていきます。
なお、バーベルの高さは完全に肘が伸びきる位置まで押し上げ、上腕三頭筋を完全収縮させてください。
【正しいやり方と手順】
①ベンチに仰向けになり、肩幅程度の狭い手幅でグリップして構える
②肘を外に張り出ず、バーベルを胸の上に下ろす
③同じ軌道でバーベルを押し上げ、肘を伸ばしきり上腕三頭筋を完全収縮させる
●バーベルフレンチプレス

バーベルフレンチプレスは上腕三頭筋に効果的なバーベルトレーニングです。
バーベルフレンチプレスは、フラットベンチに仰向けになり、肩幅より狭い手幅でシャフトをグリップし、胸の上でバーベルを構えます。
そこから、肘の位置を固定し、肩関節を動かさないように気をつけて肘を曲げ、頭の後ろにバーベルを下ろしていき、再び元の位置まで上げます。
この時に、肩関節を動かすとプルオーバー系の動作になってしまい、大胸筋や広背筋に負荷が分散してしまいますので、肘の位置をしっかりと固定して動作を行ってください。
なお、肘を外に張り出すと上腕三頭筋短頭(外側)に、脇を閉めると上腕三頭筋長頭(内側)に負荷がかかります。
【正しいやり方と手順】
①ベンチに仰向けになり、胸の上でバーベルを構える
②肘の位置を固定し、肩関節を動かさないようにバーベルを頭の後ろに下ろす
③同じ軌道で肘を伸ばして、胸の上にバーベルを戻す
■背筋群のバーベルトレーニング
●バーベルデッドリフト

バーベルデッドリフトは筋トレBIG3の一つで、背筋群に高負荷のかけられるバーベルトレーニングです。
バーベルデッドリフトは、非常に高い負荷で背筋群を鍛えられるトレーニング方法ですが、その反面、フォームを誤ったまま行うと、とても高い負担が腰や膝にかかり怪我のリスクが高い種目ですので、正しいフォームで行うことが必須の種目です。
本種目には、足の置き方とグリップの仕方で主に二つのスタイルがあり、それぞれの名称と特徴は以下の通りです。
〇ルーマニアンス(ヨーロピアン)スタイル
肩幅よりも狭く構えた足の両側をグリップするスタイルで、背筋群の動員率が高く、背中のトレーニングとして行うのに適しています。
〇ワイドスタンス(スモウ)スタイル
大きく開いて構えた足の内側をグリップするスタイルで、下半身の動員率が高く、高重量を挙上することを目的として行うのに適しています。
いずれのスタイルでも、基本的なフォームは同じで、まずは、足首がシャフトに触れる位置まで前進し足位置を決めます。
次に胸を張り、背すじを伸ばしてシャフトをグリップし、膝がつま先よりも前に出ないように、お尻を突き出して構えます。
初動は、背中で行うのではなく脚力を使ってバーベルを床から浮かせます。この時に、背中が丸まると腰に強い負担が加わりますので、目線を上にして顎を上げて引き始めます。
また、膝とつま先の向きが同じになるようにすることも膝関節保護のために重要で、内股や外股での動作は避けてください。
バーベルが浮いたら、上を見たまま背中も使ってバーベルを引き上げていき、引き上げた位置で肩甲骨を寄せきって背筋群を完全収縮させます。
バーベルを下ろす時は、一般的な筋トレ種目と違い、ゆっくりと下ろす必要はありませんが、バーベルが床でバウンドしない程度にはコントロールして戻してください。
【正しいやり方と手順】
①足首がシャフトに触れる位置まで前進し、胸を張り背すじを伸ばしてシャフトをグリップする
②膝がつま先より前に出ないように、お尻を突き出す
③背中が丸くならないように上を向く
④膝とつま先の向きを揃え、初動は脚力で引き始め、バーベルが浮いたら背中の筋力も使っていく
⑤ベーベルを引き上げたら、肩甲骨を寄せきり背筋群を完全収縮させる
なお、デッドリフトもバーベル筋トレの基本となる種目ですので、はじめから自己流の癖をつけず、専門家による情報を知った上で取り組むことが大切です。

▼全日本王者執筆記事
【デッドリフトのやり方とフォーム】種類別に効果的なセットメニューを元全日本王者が解説
●ベントオーバーローイング

バーベルベントオーバーローイングは背筋群全体に効果的なバーベルトレーニングです。
バーベルベントオーバーローイングは、肩幅程度の手幅でバーベルシャフトをグリップし、胸を張り、背すじを伸ばし、膝を曲げ、お尻を突き出した前傾姿勢をとります。
これを「ニーベントスタイル」と呼び、多くのトレーニング種目の基本となる姿勢です。
ニーベントスタイルのポイントは、「背中が丸まらないように上を見る」ことと「膝をつま先より前に出さない」ことで、これにより腰と膝に負担がかかるのを防ぎます。
ニーベントスタイルでバーベルを保持して構えたら、バーベルを引き上げていきますが、この時に、バーベルの中心ができるだけヘソの垂直線下に近い位置を保ったままの軌道で引き上げることが重要です。
具体的には、太ももの表面をバーベルシャフトが擦りながら引き上げてくる軌道になります。
バーベルをヘソの近くまで引き上げたら、肩甲骨を寄せきって背筋群を完全収縮させてください。
そして、ある程度コントロールした速度で元に戻ります。
【正しいやり方と手順】
①肩幅程度の手幅でバーベルをグリップし、胸を張り背すじを伸ばし、お尻を突き出した前傾姿勢(ニーベントスタイル)で構える
②太ももに沿わせてバーベルを引き上げる
③肩甲骨を寄せきり背筋群を完全収縮させる
④コントロールしながら元に戻る
●バーベルシュラッグ

バーベルショルダーシュラッグは僧帽筋に集中的な効果があるバーベルトレーニングです。
バーベルショルダーシュラッグは胸を張り、背すじを伸ばし、腕を下ろした位置で肩幅程度の手幅でバーベルをグリップして構えます。
そこから、肩をすくめるような動作で肩甲骨を引き寄せながらバーベルを引き上げていきますが、この時に肩関節や肘関節を動かさないようにするのがポイントです。
肩関節を動かすと広背筋に、肘関節を動かすと上腕二頭筋にそれぞれ負荷が分散してしまいますので、肩や肘は動かさず、肩甲骨を引き寄せる動作だけに集中してください。
そして、バーベルを引き上げながら、肩甲骨を寄せきり僧帽筋を完全収縮させたら、ゆっくりと効かせながら元に戻ります。
【正しいやり方と手順】
①胸を張り背すじを伸ばし、肩幅程度の手幅でバーベルをグリップして構える
②肩や肘を動かさないように気をつけ、肩甲骨を引き寄せる動作だけでバーベルを引き上げる
③肩甲骨を寄せきり僧帽筋を完全収縮させる
④ゆっくりと効かせながら元に戻る
●ストレートアームバーベルプルオーバー

ストレートアームバーベルプルオーバーは、肘を伸ばしたまま行うバリエーションで、広背筋に負荷がかかります。
仰向けになり、やや広めの手幅でシャフトをグリップし、バーベルを胸の上で構えます。
そこから、肘を伸ばしたままバーベルを頭の後ろに最大限下ろしたら、息をためたままバーベルを引き上げていきます。
そして、最後に肩甲骨を引き寄せて広背筋を完全収縮させてください。
【正しいやり方と手順】
①仰向けになり、やや広めのグリップでバーベルを胸の上に構える
②肘を伸ばしたままバーベルを頭の後ろに下ろす
③肘を伸ばしたままバーベルを引き上げていき、最後に肩甲骨を引き寄せて広背筋を完全収縮させる
●バーベルグッドモーニング

バーベルグッドモーニングは脊柱起立筋に集中的な効果があるバーベルトレーニングです。
バーベルグッドモーニングは、高負荷で脊柱起立筋を鍛えられる種目ですが、フォームを間違えると腰を痛めたり、転倒のリスクが高い種目ですので、十分に練習をして取り組んでください。
まず、肩の後ろでバーベルを担ぎ、胸を張り背すじを伸ばし、肩幅程度の足幅で構えます。
そこから、上半身を前に倒していきますが、この時に背中が丸くならないようにすることが、腰を痛めないために非常に重要です。背中が丸くならないためには、「胸を張る意識をする」ことと「顎を上げて上を見る」ことが効果的です。
また、上半身を倒すのは最大でも床と並行までにしてください。それ以上倒すと、転倒のリスクがあります。
なお、本種目は高重量で行うのには適しておらず、15レップ前後が行える中~低負荷でじっくりと効かせるのが一般的です。
【正しいやり方と手順】
①バーベルを肩の後ろに担ぎ、胸を張り背すじを伸ばし、肩幅程度に足を開いて構える
②背中が丸くならないよう、上を見て上半身を倒す
③上半身を床と並行になるまで倒したら、ゆっくりと元に戻る
■上腕二頭筋のバーベルトレーニング
●バーベルカール

バーベルカール上腕二頭全体に効果的な基本となる腕のバーベルトレーニングです。
バーベルカールは肩幅程度の手幅でバーベル持ち、胸を張り、背すじを伸ばして構えます。
そこから、肘を前後に動かさないように固定して、肩関節が動くのを防ぐとともに、上半身を後ろに傾けないように気をつけてバーベルを持ち上げます。
肩関節が動いたり、上半身を反らせたりすると負荷が僧帽筋に分散してしまいますので、肘の位置をしっかりと固定し、直立姿勢を保って動作を行ってください。
また、本種目はバーベルを持ち上げる時のコンセントリック収縮(短縮性収縮)だけでなく、バーベルを下ろす時にゆっくりとウエイトに耐えながら、上腕二頭筋にエキセントリック収縮(伸長性収縮)を加えることも大切なポイントです。
【正しいやり方と手順】
①胸を張り、背すじを伸ばし、バーベルを保持して構える
②肘の位置を動かしたり、上半身を反らせたりしないように気をつけてバーベルを持ち上げる
③バーベルを持ち上げたら、その位置で前腕を回外回旋させて上腕二頭筋を完全収縮させる
④ゆっくりと効かせながら元に戻る
●バーベルプリチャーカール

バーベルプリチャーカールは上腕二頭筋に効果的なバーベルトレーニングです。
バーベルプリチャーカールは、専用のカール台に上腕を置き、バーベルをグリップして構えますが、カール台に置くのはあくまでも上腕であり、肘ではないので注意してください。
肘だけをカール台に置いて動作を行うと、多くの場合、無意識に肘を支点としたテコ動作を加えてしまい、筋力トレーニングではなく単なる「バーベルを保持した前後動作」になってしまうので注意が必要です。
このためには、上腕をカール台に置くことに加え、上半身を前のめりにしないことが重要で、上半身は垂直を保ったままでトレーニングを行います。
また、足を踏ん張らないことも大切で、足を踏ん張ると、つい上半身を後ろに傾けてテコ動作を使ってしまいますので、足を投げ出した状態で、純粋に上腕二頭筋の筋力だけで動作を行ってください。
なお、本種目はEZバーを下ろす時に、勢いで下ろすのではなくウエイトに耐えながら、上腕二頭筋長頭にエクセントリック収縮(伸張性収縮)を加えることも非常に重要です。
【正しいやり方と手順】
①カール台に座り、上腕を台に置き、バーベルをグリップして構える
②上半身を前後させず、足も踏ん張らず、上腕二頭筋の筋力だけでバーベルを上げる
③ゆっくりと効かせながら元に戻る
●バーベルリバースカール

バーベルリバースカール前腕筋群に効果的なバーベルトレーニングです。
バーベルリバースカールは通常のバーベルカールとは逆に、手の平が下を向くようにバーベルをグリップして構えます。
そこからバーベルを上げていきますが、この時に肘の位置を固定して肩関節を動かさないようにするとともに、上半身を反らせたりしないようにしてください。
肩関節が動いたり、上半身を後ろに傾けると負荷が僧帽筋に逃げてしまいます。
バーベルを持ち上げたら、その位置で手首を上に反らせるようにスナップ動作を加えることで、前腕伸筋群が強く収縮して効果が高まります。
【正しいやり方と手順】
①胸を張り、背すじを伸ばして構える
②肘の位置を固定し、肩関節が動かないように注意してバーベルを持ち上げる
③バーベルを持ち上げたら、その位置で手首を反らせるスナップを加える
④ゆっくりと効かせながら元に戻る
●バーベルドラッグカール

バーベルドラッグカールは上腕二頭筋短頭に高負荷をかけられるコンパウンド(複合関節)バーベルトレーニングです。
バーベルドラッグカール、基本的にはアイソレーション種目(単関節運動)であるバーベルカールにおいて、意図的に肘を引いて高重量を上腕二頭筋にかけるコンパウンド種目(複合関節運動)とした種目です。
まず、胸を張り、背すじを伸ばし、バーベルを保持して構えたら、そこからまず肘が90度前後になるまでは肘の位置を固定してバーベルを持ち上げます。
そして、肘の角度が90度前後になったら、肩をすくめるように肘を後ろに引き、可能な限りバーベルを高く持ち上げます。
この時に、上腕二頭筋を強く意識して筋肉を完全収縮させてください。
上腕二頭筋が完全収縮したら、同じ軌道でゆっくりと効かせながら元に戻ります。
【正しいやり方と手順】
①胸を張り、背すじを伸ばして構える
②肘が直角程度になるまでは、肘の位置を固定して肘から先だけでバーベルを持ち上げる
③肘が直角程度になったら、肩をすくめるように肘を後ろに引き、上腕二頭筋を完全収縮させる
④ゆっくりと効かせながら元に戻る
●EZバーハンマーカール

EZバーカールは上腕二頭筋長頭に集中的な効果があるバーベルトレーニングです。
EZバーカールは、特殊な形状をしたEZバーを縦にグリップ(ハンマーグリップ)するバーベルカールの一種です。EZバーにはさまざまな握り方がありますが、本記事では上腕二頭筋長頭をターゲットにしたハンマーグリップでのバリエーションを解説します。
まず、胸を張り背すじを伸ばし、バーを縦にグリップして構えます。そこから、肘の位置を固定し、肘を曲げてバーベルを上げていきますが、この時に「肘の位置を動かさない」ことと「上半身を反らせない」ことが大切です。
肩関節が動き、肘の位置が前後に動くフォームや、上半身を反らせたフォームで行うと負荷の多くが僧帽筋に分散してしまいますので、真っ直ぐに立ち、肘の位置をしっかりと固定して動作を行ってください。
また、本種目はEZバーを下ろす時に、勢いで下ろすのではなくウエイトに耐えながら、上腕二頭筋長頭にエクセントリック収縮(伸張性収縮)を加えることも重要です。
【正しいやり方と手順】
①胸を張り背すじを伸ばし、EZバーを縦にグリップして構える
②肘の位置を固定し、上半身を反らせずに肘を曲げる
③ゆっくりと効かせながら元に戻る
■下半身のバーベルトレーニング
●バーベルスクワット

バーベルスクワットは、下半身全体に効果的な下半身バーベル筋トレの基本となるトレーニングです。
バーベルスクワットは下半身に対して非常に効果の高いトレーニングですが、やり方を間違えると腰や膝を痛めるリスクがありますので、事前に十分にフォーム練習を行ってから取り組んでください。
バーベルスクワットは、まず胸を張り、背中が丸まらないように背筋を伸ばして構え、肩の後ろにバーベルを保持して、そこからしゃがんでいきます。背中が丸まった状態で行うと、腰を痛めるリスクがありますので注意しましょう。
しゃがむときは、膝関節に負担がかからないよう、膝がつま先より前に出ないことを意識し、お尻をやや突き出して斜め後ろにしゃがんでいきます。
ちょうど、椅子に座る軌道と動作をイメージしてください。
また、膝がつま先の方向を常に向いていることも大切で、つま先と膝の向きが違うと膝関節に捻れ負荷がかかります。必ず膝とつま先の向きは揃えましょう。
そして、太ももが床と平行になるまでしゃがんだら、そこから立ち上がっていきますが、この時に顎を上げて上を見るようにすると、背中が丸まらずに正しいフォームになります。
【正しいやり方と手順】
①胸を張り、背筋を伸ばしてバーベルを持って構える
②膝がつま先より前に出ないように意識し、お尻をやや突き出して斜め後ろにしゃがむ
③太ももが床と平行になるまでしゃがんだら、上を向いて立ち上がる

▼全日本王者執筆記事
【バーベルスクワットのフォームとメニュー】元全日本王者が効果的な回数・セット数も解説
●バーベルフロントランジ

バーベルフロントランジはハムストリングスに効果的なバーベルトレーニングです。
バーベルフロントランジは、バーベルを肩の後ろで担ぎ、胸を張り背すじを伸ばし、足を大きく前後に開いて構えます。そこから、前足を曲げて前方にしゃがんでいきますが、この時に膝がつま先よりも前に出ないように気をつけてください。膝がつま先よりも出てしまうと、膝関節と靭帯に大きな負担となります。
前足の太ももが床と平行になるまでしゃがんだら、後ろにした脚に意識を集中し、後ろ足で身体を引き寄せるようにして立ち上がります。
なお、本種目は足の置き方を変えて、合わせて1セットになりますが、構えにくい足の置き方から先に行ったほうが、足の置き方を変えてからの後半でセットを完遂しやすくなります。
【正しいやり方と手順】
①胸を張り、背すじを伸ばして、足を前後に大きく開いて構える
②前足の膝がつま先よりも前に出ないように気をつけてしゃがむ
③前足の太ももが床と平行になるまでしゃがんだら、後ろ足で身体を引き寄せるようにして立ち上がる
●バーベルサイドランジ

バーベルサイドランジは内転筋群に集中的な効果のあるバーベルトレーニングです。
バーベルサイドランジバーベルサイドランジは、肩の後ろでバーベルを担ぎ、胸を張り背筋を伸ばし構えます。
そこから、片方の足を曲げて横方にしゃがんでいきますが、この時に膝に負担をかけないように、膝がつま先よりも前に出ないように気をつけ、また、膝とつま先の向きを同じにしてください。
曲げたほうの脚の太ももが床と平行になるまでしゃがんだら、伸ばしたほうの脚で身体を引き寄せるようにして立ち上がります。
そして、元に戻ったら反対側へ同じようにしゃがみ、再び立ち上がります。
【正しいやり方と手順】
①胸を張り、背すじを伸ばし、大きく開いた足の間でバーベルを保持して構える
②膝がつま先より前に出ず、なおかつ、つま先と膝が同じ方向を向くように気をつけて横方向へしゃがむ
③曲げたほうの脚の太ももが床と平行になるまでしゃがんだら、伸ばしたほうの脚で身体を引き寄せるようにして立ち上がる
④逆方向へしゃがみ、同様に立ち上がる
●バーベルブルガリアンスクワット

バーベルブルガリアンスクワットは、ブルガリアの体操五輪チームが発案したとされる高強度のスクワットバリエーションで、スプリットスクワットとも呼ばれています。
バーベルブルガリアンスクワットブルガリアンスクワットは、片足を前に出し、片足を後ろにして足の甲を台などに乗せ、バーベルを肩の後ろに担いで構えます。
そこから、胸を張り、背すじを伸ばして斜め後ろにしゃがんでいきます。そのまま真下にしゃがむと、負荷が下半身背面にかかりにくいので、必ず斜め後ろにしゃがむのがポイントです。
また、この時に前にした脚の膝がつま先より前に出ないように気をつけてください。膝が飛び出したフォームになると、膝関節に強い負担がかかり、痛めるリスクがありますので、十分に注意しましょう。
前にした脚の太ももが床と平行になるまでしゃがんだら、そこから立ち上がっていきますが、この時に後ろにした脚を主働にして立ち上がるのが、下半身背面に効かせるための大切なコツです。
なお、本種目は足の置き方を変えて、合わせて1セットになりますが、構えにくい足の置き方から先に行ったほうが、足の置き方を変えてからの後半でセットを完遂しやすくなります。
【正しいやり方と手順】
①胸を張り、背筋を伸ばし、片足を前にもう片足を後ろにして構える
②後ろにした脚に負荷がかかるよう、斜め後ろにしゃがむ
③前にした脚の膝がつま先より前に出ないように気をつけて、太ももが床と平行になるまでしゃがむ
④後ろにした脚に意識を集中して立ち上がる
■具体的な一週間のプログラム
それでは、ここからは筋トレbig3を中心とした具体的な週3回のトレーニングプログラムを例示していきます。
●週1回目のバーベルトレーニング
・ベンチプレス中心に上半身の押す筋肉の日
①バーベルベンチプレスを2~3セット
②ワイドグリップベンチプレスまたはデクラインベンチプレスを1~2セット
③インクラインベンチプレスまたはリバースグリップベンチプレスを1~2セット
④バーベルショルダープレスまたはバーベルアップライトローを2~3セット
⑤バーベルフロントレイズを1~2セット
⑥バーベルリアデルタローを1~2セット
⑦ナローベンチプレスまたはバーベルフレンチプレスを2~3セット
●週2回目のバーベルトレーニング
・スクワット中心に下半身の筋肉の日
①バーベルスクワットを2~3セット
②バーベルフロントランジまたはバーベルブルガリアンスクワットを2~3セット
③バーベルサイドランジを2~3セット
●週3回目のバーベルトレーニング
・デッドリフト中心に上半身の引く筋肉の日
①バーベルデッドリフトまたはベントオーバーローイングを2~3セット
②バーベルシュラッグを1~2セット
③バーベルプルオーバーを1~2セット
④バーベルグッドモーニングを1~2セット
⑤バーベルカールまたはバーベルプリチャーカールを2~3セット
⑥EZバーカールを1~2セット
⑦バーベルドラッグカールを1~2セット
⑧バーベルリバースカールを1~2セット
自宅筋トレ方法|大胸筋の筋トレ
自重筋トレ方法|背筋群の筋トレ
チューブ筋トレ|三角筋の筋トレ
ダンベル筋トレ|三頭筋の筋トレ
マシーン筋トレ|二頭筋の筋トレ
バーベル筋トレ|腹筋群の筋トレ
筋肥大筋トレ法|下半身の筋トレ
---------------
■バーベル筋トレにおすすめのグッズ
●バーベルセット

当ジムではラバータイプのオリンピックバーベルを中心として使用しています。リーズナブルな価格設定なので、家庭用としてもおすすめです。
▼詳しく見る
●リストラップ

手首を補助し、効率的なプレス系トレーニングに必須とも言えるのがリストラップで、目的・レベルに応じてさまざまなタイプがあります。
▼詳しく見る
●エイトストラップ&パワーグリップ

握力を補助するトレーニング用品として、圧倒的なサポート力のエイトストラップやクイックな装着が魅力のパワーグリップなどがあり、プル系トレーニングのマストアイテムです。
▼詳しく見る
おすすめのエイトストラップ&パワーグリップ|武器屋・鬼&GLFIT公式
●トレーニングベルト

腰を物理的にサポートするだけでなく、腹圧を高めて最大筋力を向上させるトレーニングベルトは、筋トレにおいて最も重要なアイテムで、目的・レベルにあわせてさまざまなタイプがあります。
▼詳しく見る
●エルボースリーブ

多くのトレーニーが抱える悩みが肘の問題ですが、こちらのエルボースリーブは並行巻きからX巻きまででき、個人にあわせたサポートが可能です。
▼詳しく見る
■全バーベル種目一覧
バーベルベンチプレス
ワイドグリップベンチプレス
インクラインベンチプレス
デクラインベンチプレス
リバースグリップベンチプレス
バーベルデッドリフト
ベントオーバーローイング
バーベルシュラッグ
バーベルプルオーバー
バーベルグッドモーニング
バーベルショルダープレス
バーベルアップライトロー
バーベルフロントレイズ
バーベルリアデルタロー
ナローベンチプレス
バーベルフレンチプレス
バーベルカール
EZバーカール
バーベルプリチャーカール
バーベルリバースカール
バーベルドラッグカール
バーベルスクワット
バーベルフロントランジ
バーベルサイドランジ
バーベルブルガリアンスクワット
※当サイトの表現するバルクアップとは筋肥大、バストアップとは胸の土台となる大胸筋のバルクアップ、ダイエットとは健康的な体脂肪率の減少、引き締めとは食事管理と合わせた総合的なダイエットを指します。
【執筆者情報】上岡岳|日本アームレスリング連盟常任理事|元日本代表|国際レフリー|ジムトレーナー|生物学学芸員